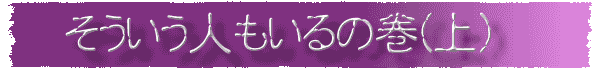 |
ヴェルディおじさんと初めて会ったのは、秋も深まったある日曜日のことだった。 その週末はなぜか遠出をせずに、安下宿の同居人S氏とともに、昼下がりのフィレンツェ中心部をうろつき、店々のショーウィンドウを眺めていた。 ちなみに、イタリアの店というのは、どんな小さな店にもきちんとしたショーウィンドウがついている。庶民的な靴屋からブランド服を扱うブティックまで、こんな小さな店にこんな大きなショーウィンドウが----と驚くほどだ。 しかも、ひどく実用的である。よほど気取った超有名ブランド直営のブティックは別として、扱っている商品が、ショーウィンドーにところ狭しと並べられているのだ。 「だから、店に入るということは、そこで買うと決めたときに限るんや。買うかどうかも決めずに入って、あれこれとキョロキョロしたらいかんで」 と、日本で輸入ブランドの品物を扱う仕事をしていたS氏は、先生のような口調で私に教えてくれた。 「ほら、値札も必ずついてるから、そこで扱っている品物がひとめでわかるんや。なかなかいいシステムやろ」 彼は、それがまるで自分の手柄でもあるかのように、得意気であった。 |

|
店が閉まっていても、ショーウィンドーは見られるようにしているところも多い。 だから、貧乏学生だった私にとって、タダでヒマがつぶせて目の保養にもなるウィンドーショッピングは、昼の散歩に欠かせない日課となっていたのである。しかも、S氏といっしょに散歩をすれば、服や靴についてのウンチク付きだ。ときに説教臭くなるのさえ我慢すれば、ファッションのいい勉強になった。 |
|
| 夜もショーウィンドーがあかあかとしているので、散歩をしていてもあきない。 撮影 : 1981/11 Firenze |
||
|
それにしても、ショーウィンドーに対するS氏の執着ぶりは、余人には計り知れないものがあった。気に入った店があると、つっとショーウィンドーのガラスの前に立ち、そのややくぼんだ目で、中の品物をじっと見渡すのである。声をかけるのがはばかられる雰囲気だ。それは店の在庫担当者もかくやと思えるほどの真剣さであった。 そんな姿を、まだ私は後ろから見ているからいいようなものの、もし店の中から見ていた人がいたら、さぞかし不気味だったに違いない。 私は思ったものだった。 ----こりゃ、ひょっとすると、フィレンツェじゅうの店で評判になっているかもしれないぞ。毎日、恐い顔をしてショーウィンドーを覗いている変な東洋人がいるって……。 さて、その日のウィンドーショッピングも一段落したところで、ふとまわりを見ると知った顔があった。クラスは違うが、私たちの学校に通っている日本人のフミコさんである。彼女は道のまんなかで、4、5人のイタリア人男性と親しげに話をしていたところであった。 「やあやあ、こんにちは」 「あら、Sさんにダガシさんじゃないの。紹介するわ、○○さんに、××さんに……」 ちなみに、フィレンツェというと大都会だと思われるようだが、旧市街の範囲は狭く、しかも中心部はそのまた一部分である。だから、知人に会うのはちっとも珍しくない。こんなことも、東京で生まれ育った私にとっておもしろい体験であった。 さて、フミコさんの紹介に従って、いつものように「初めまして、ダガシと申します」などと言いながら、次々に握手をしていった私である。 イタリア人のグループは、若い人で20代後半、最年長の人は60代なかばといったところだろうか。この最年長の人が、その後も何度か顔を合わせることになるヴェルディおじさんだったわけである。 |
|
| 市の中心部から、アルノ川を渡ればボーボリ庭園はすぐ。 ここからの市内の眺めもまたいい。 撮影 : 1990/09 Firenze |

|
|
彼らはどういう関係なのかはわからなかったが、誰もが手ぶらで普段着でいたところから、地元の人だということはわかった。 それにしても、ぽっちゃりして人なつこいところはあるが、あまり男とは縁がなさそうに思えたフミコさんである。どこで、こんなお兄さんやおじさんたちと知り合ったか、私は疑問に思ってたずねてみた。 「それがさあ、いまこのあたりで散歩していたら、声をかけられたのよ」 いかにもイタリア人らしい話である。 とはいえ、彼らはけっしてうわついたような人たちではなく、むしろいわゆる典型的なイタリア人とは違って、もの静かな人たちばかりであった。会話は低い声で交わされ、ときおり笑いがまじるものの、けっして必要以上に気分が高まることはない。 フィレンツェは古都なので、そこに住む人は、よく言えば落ちついていて、悪く言えば気取っているなどと言われているが、まさにそんな人たちであった。 しばしのあいだ、みんなでとりとめのないことを話していると、突然だれかが声をあげた。 「どうだい、せっかくだから、きょうの夕方あたりボーボリ庭園にでも行ってみようじゃないか」 「おお、それがいい。どうだ、君たちはヒマかい。そうか、そうか、じゃあ、ポンテ・ヴェッキオ(ヴェッキオ橋)のこっち側に4時に集合だ」 こうして、ほとんど私たちの意向を確かめることなく、その日の夕方の散歩がいきなり決まってしまった。私はといえば、ボーボリ庭園には行ったばかりだったので、あまり乗り気ではなかったのだが、その場の勢いでうなずいてしまったのである。 まだまだ自己主張がたりない駄菓子青年であった。 (つづく) |
| ▲前のページに戻る | 次のページに進む▼ |
| ■トップページ | | | 「イタリア貧遊記」表紙■ |