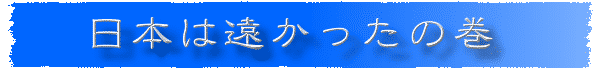 |
午前中は西洋人の多い語学学校へ通い、午後になるとアラブ人やアフリカ人がたむろする建物に顔を出してボランティアの会話教室に通う--こんな生活が2か月ほど続いた。 おっかなびっくり通いはじめた難民学校だったが、半月もして知り合いもふえてくると、まるで十年も前からいたようなデカい顔をして、たむろするようになった私である。 やがて、S氏が日本から来るお客さんからもらった週刊誌を集会室でまわし読みしながら、金をかけずにヒマをつぶす術も覚えていった。 難民学校で一番多いのがアラブ人学生。授業中も騒がしくて困った人たちなのだが、「戦乱の祖国を離れて厳しい生活をしているからだから、大目に見てやろう」なんて思っていた。 しかし、いろいろと話をしていくと、どうもそうではないらしい。彼らの大多数は、アルバイトをしているようでもなく、何か月も何年もフィレンツェにいるのだ。 「もしかしたら、彼らはいいところのお坊ちゃんじゃないんですか」 「うーん、中近東の小金持ちのが、息子をイタリアにやっているのかもしれんなあ。それにしても、自分の息子がイタリアにまで来て、日がな卓球をして遊んでいるとは知らんやろうなあ」 まあ、自分たちのことを棚にあげて、よけいなお世話をしている私たちであった。 ところで、休憩室には毎日のメッカへのお祈りの時間を示すプリントがあったが、実際に彼らがお祈りをしているところは一度も見たことがなかった。 |
|
まあ、なんだかんだいっても、一番気があうのは東洋人である。アジアの端っこでは、お互いに相違点ばかりを見いだそうとしている節があるが、ヨーロッパに来てしまえば親戚のようなものである。 そもそもほとんどのイタリア人が、日本人も中国人も韓国人も区別はつかない。少なくとも、1981年には区別がつかなかった。 あるとき、私とS氏、T島氏、そして香港出身のシャン氏の4人が、難民学校のふかふかした、しかしところどころ穴のあいている椅子に座って、イタリア語でとりとめのない話をしていたときである。 |

| |
| 夕暮れのフィレンツェの中心部。散歩や買い物をする人がだんだんと増えてくる。 撮影 : 1981/11 Firenze |
||
|
たまに顔を見せるポルトガル人が近くによってきた。 「なんでお前たちはイタリア語で話しているんだ」 「いやあ、中国語と日本語は全然ちがうから、会話が通じないんだよ」 すると、彼は得意そうにいった。 「すると、お前たちは、自分たちのことばとイタリア語と英語くらいしか話せないのか。オレはポルトガル語、イタリア語、スペイン語、フランス語、英語、ドイツ語が話せるぞ。お前らは努力が足りないじゃないか」 なんて、偉そうなことをいっていたのだが、まったく困ったものである。そんなのは、方言みたいなもんである。それなら、祖母ちゃんの使っていた福島弁なら話せるし、津軽弁や薩摩弁は難しいけれど、新潟弁や大阪弁くらいならば聞いてだいたいわかる。 ……と抗弁しようとも思ったが、イタリア語も英語もへたなのが心の隅に引っかかって、何にも言えなかった私である。 「それはそうと、誰かジュウドーをやっているヤツはいるか?」 私たちは顔を見合わせた。一人ひとりと目があったが、みんな「うー」とか「のー」とかいいながら首を横に振るばかり。 「じゃあ、カラテは?」 やっぱり、首を横に振るだけ。すると、彼は驚いたような顔をして言った。 「なんだ、これだけ日本人と中国人が揃っていて、ジュードーもカラテもできるやつがいないのか」 重ね重ね困ったやつであった。まあ、日本や東アジアへの認識なんて、そんな程度のものであった。もしかすると、いまでもそれほど変わっていないかもしれない。 ところで、香港出身のシャンというのは、美術の勉強に来ていると話していたが、どうも勉強しているようには見えない。しかも、フィレンツェに5年もいるという。これまた、難民学校の休憩室あたりでぶらぶらしていた。 やはり、いいところのお坊ちゃんにちがいない--と、貧乏人ばかりの日本人は推測していた。 シャンは、知り合って2週間ほどもすると、私たちの安下宿によく遊びにくるようになった。殺風景な部屋のなかで、お茶も飲まずに、あれこれととりとめのない話を、お互いにへたなイタリア語でしていたものだった。 |
|

|
ヴェッキオ宮殿やウッフィツィ美術館の裏。右手奥がバルジェロ美術館。とにかくフィレンツェには美術館や博物館が多く、1年くらい滞在しないと全部を見ることはできないように思えた。 撮影 : 1981/11 Firenze |
|
東洋人以外で気が合ったのは、アフリカ人である。とくに、コートジボアールから来た学生のイブラヒムと、大柄なカメルーン人のジャーナリストとはよく話をしたものである。 ある日、S氏、T島氏と3人でフィレンツェの駅前をうろうろと歩いていると、この2人とばったり出会った。 「おお、ブォン・ジョールノ! 元気か、わっはっは!」 私たちはがっちりと握手をした。週に2、3度も顔をあわせていても、おおげさに再会を祝うのがここの流儀である。 2人と3人だから、順列組み合わせで合計6回の握手があった後、次の儀式がはじまる。 「おお、きょうはいい服を着ているじゃないか! お前にピッタリだよ」 実際、イブラヒムはいつも派手な色の服を来ていて、その日はとくにショッキングピンクのセーターを着ていたのであった。 「いやあ、Sさん、すごい色のセーターですね」 と私が言うと、 「いやあ、日本人が同じ色の服を着たらあかんけど、アフリカ人は肌が黒いから原色が似合うんや」 と、いちおうファッション業界に身を投じているS氏が説明してくれた。なるほど、そんなものかと思った私である。 まあ、こんな“人をほめる練習”をしょっちゅうしていたおかげで、日本に帰ってきてからも臆することなく女性の服装やアクセサリーをほめることができるようなった。概して、日本でもウケはよかったが、それが私の人生にどれほど役に立ったかは定かではない。 さて、そのイブラヒムは、アフリカのおみやげの人形のような愛嬌のある顔をして、難民学校でもみんなの人気者であった。 彼は、観光の勉強のためにイタリアに来ていると言っていた。 「観光の勉強が終わったら、ぜひ日本にも来いよ」 私たちが言うと、彼は答えた。 「ああ、行きたいなあ。で、日本にも有名な観光地はあるのか」 「もちろんだ。京都は世界的な観光地だ。知ってるか?」 「キョート? ……知らないなあ」 まだまだ、アフリカから日本は遠い国なのだと感じる駄菓子青年であった。 気を取り直して、私は聞いた。 「東京は知ってるだろう」 「もちろんだ」 そのとき、そばで聞いていたカメルーンのジャーナリストが口をはさんだ。 「おお、トーキョー。大きな音をたてて車が走りまわり、人びとは叫び、エネルギーとカオスに満ちた町……そうだろう。違うか?」 その話を聞いて、イブラヒムも大きな目をぱっちりとあけて、何度もうなずいている。 「う、うーん、そんな場所もあるかもしれないなあ」 と、東京の下町で育った私はあいまいな返事をしたのであった。 |
| ▲前のページに戻る | 次のページに進む▼ |
| ■トップページ | | | 「イタリア貧遊記」表紙■ |